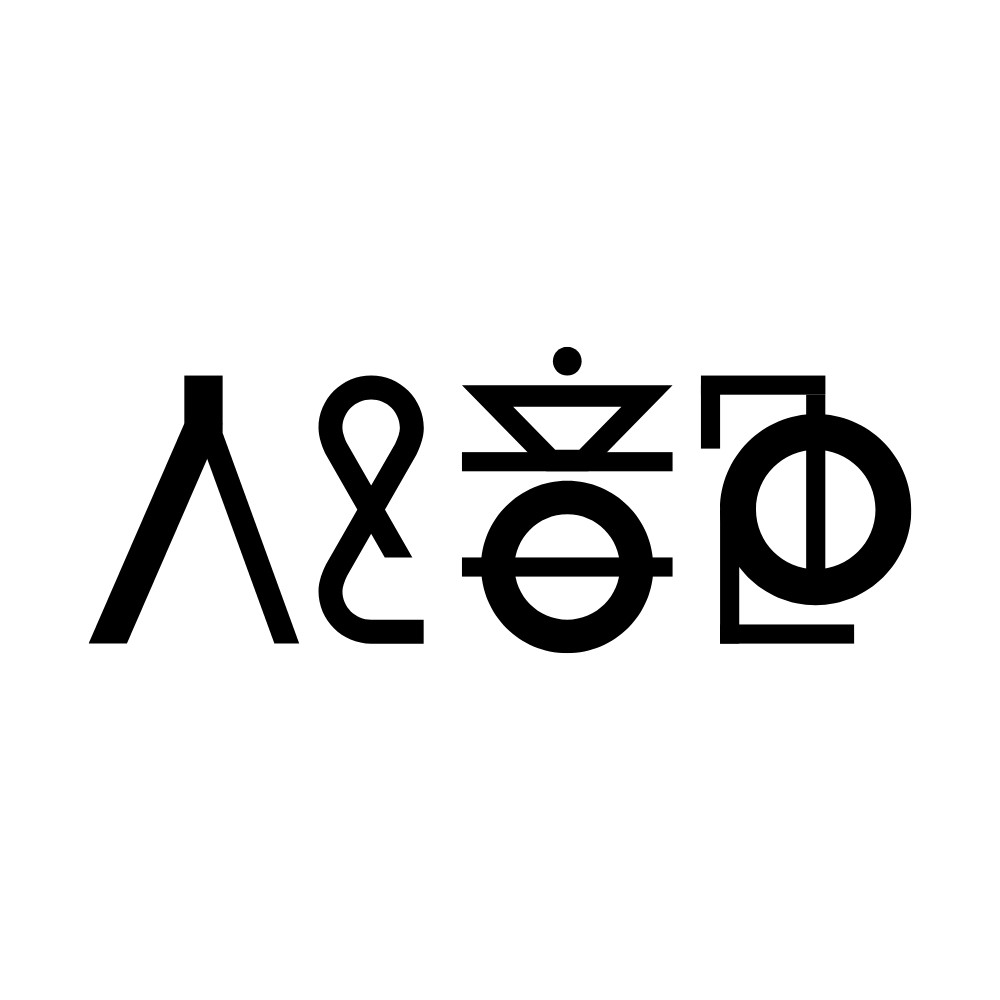現在の融資先
直近1年内に完済した融資先
該当する融資先がありません。
過去の融資先
※名称やロゴは、融資実行時のものです。

大阪府、第23期
認定NPO法人D×P

大阪府、第23期
NPO法人プラスWe

福岡県、つなぎ
日本自然農業協会

滋賀県、第25期
パレスチナ・アマル

宮城県、第22期
合同会社ビーバー

兵庫県、第19期
特定非営利活動法人 二求の塾

兵庫県、第19期
合同会社 NICONICOYASAI

大阪府、つなぎ
一般社団法人みずとわ

京都府、つなぎ
南丹地立計画協議会 船技郷企画部

大阪府、第17期
NPO法人SilentVoice
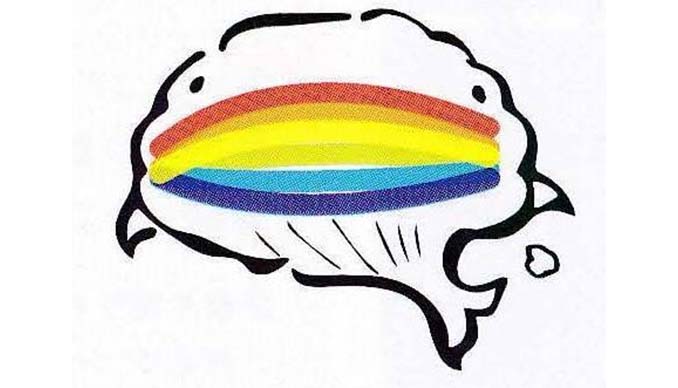
京都府、第16期
一般社団法人くじら雲

滋賀県、第15期
合同会社nimai-nitai

大阪府、第14期
認定NPO法人箕面こどもの森学園

宮城県、つなぎ
一般社団法人 復興応援団

兵庫県、つなぎ
兵庫県有機農業活性化協議会

東京都、第10期
株式会社 和える
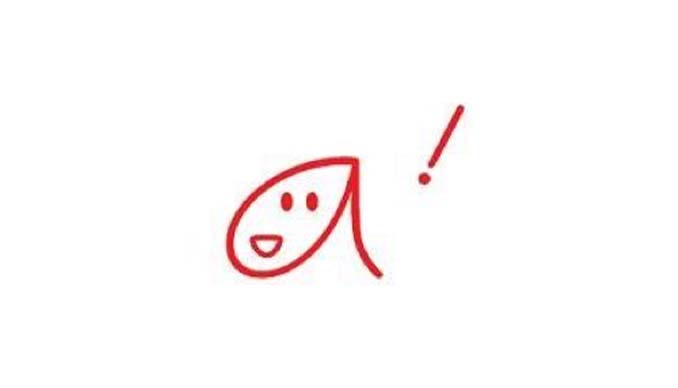
岩手県、つなぎ
到底非営利活動法人 まぁむたかた

東京都、第10期
特定非営利活動法人 グリーンズ

東京都、第11期
株式会社 Hub Tokyo

東京都、第11期
株式会社ラボアンドタウン

東京都、第11期
株式会社ウィルモア

大阪府、第11期
一般社団法人スマイルゲート

兵庫県、第7期
フォームアンドカンパニー株式会社
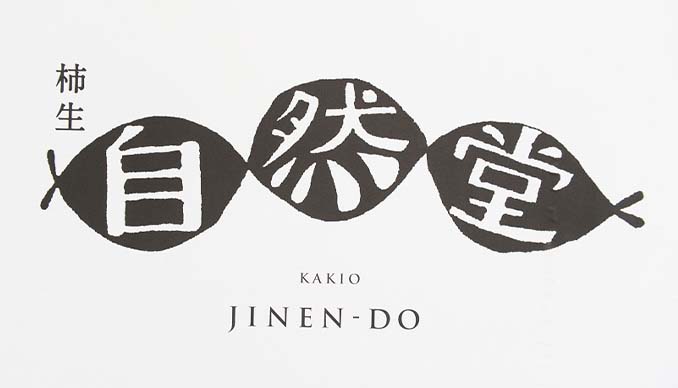
神奈川県、第6期
一般社団法人働くしあわせプロジェクト

大阪府、第1期
株式会社坂ノ途中

東京都、第5期
株式会社ロクマル

東京都、第4期
株式会社Micro Nations

兵庫県、つなぎ
兵庫県有機農業生産出荷組合
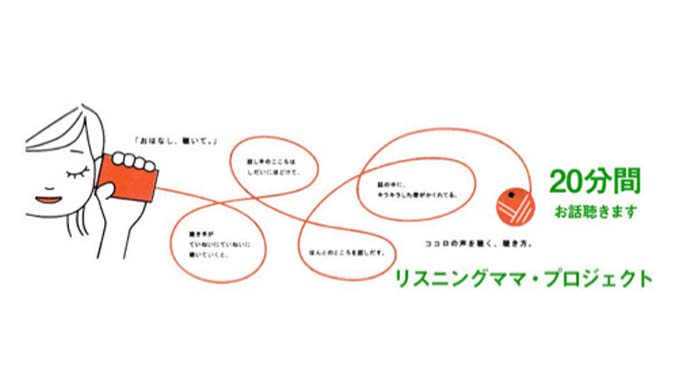
東京都、第4期
タンジェリン

大阪府、第4期
特定非営利活動法人ノーベル
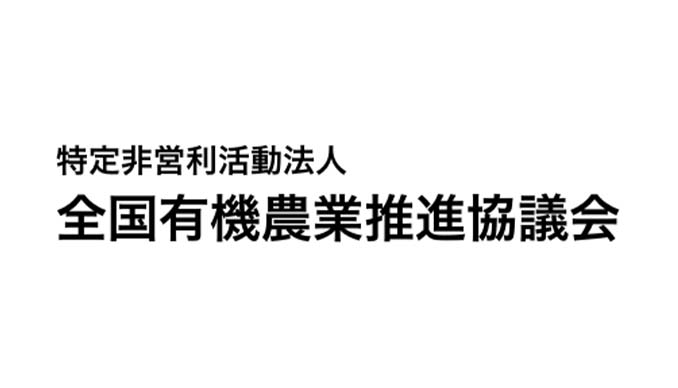
東京都、つなぎ
特定非営利活動法人 全国有機農業推進協議会
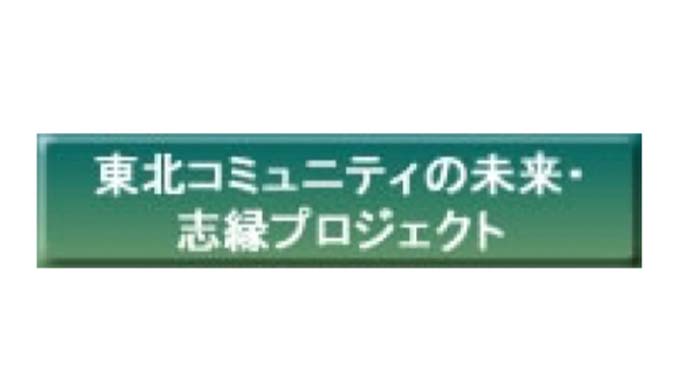
埼玉県、つなぎ
東北コミュニティの未来・志緑プロジェクト

千葉県、つなぎ
特定非営利活動法人発達わんぱく会

岡山県、第3期
特定非営利活動法人英田上山棚田団
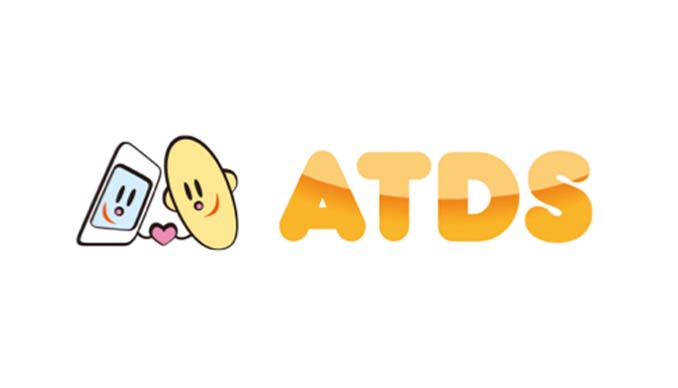
京都府、第2期
NPO法人 支援機器普及促進協会(旧memis)
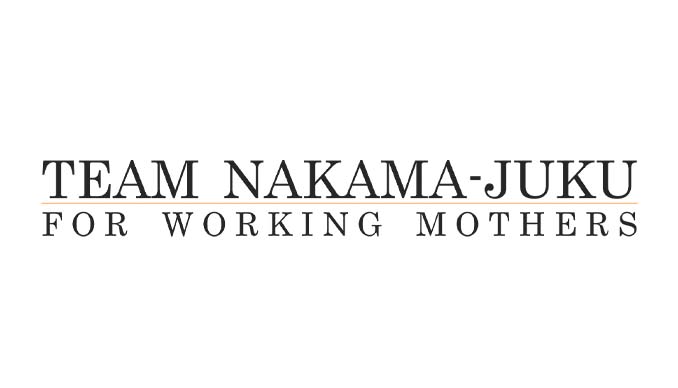
大阪府、第2期
株式会社エム・ディ・アイ

京都府、第2期
特定非営利活動法人エクスクラメーション・スタイル

北海道、つなぎ
neeth株式会社

京都府/第1期
株式会社オモレイ

東京都、第1期
株式会社ソノリテ