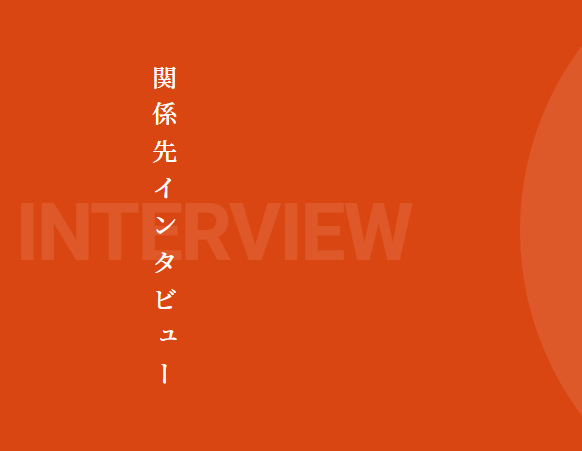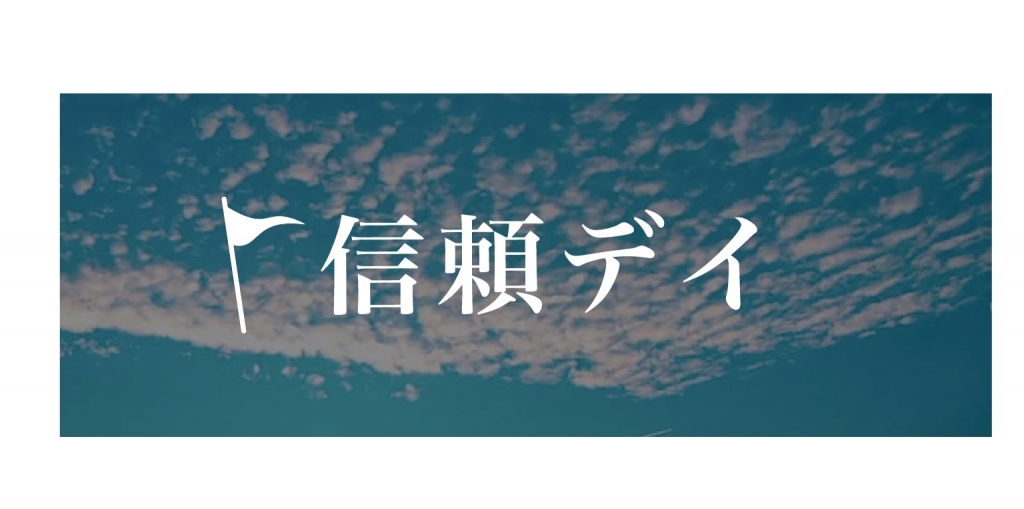
■【信頼デイ】とは?
「信頼デイ」は、人と人が助け合っていく関係性=社会関係資本を「信頼資本」「共感資本」と名づけてきた当財団が、この資本=元手がもっと活用される社会に向けた動きの一環として、ネットワークを作り、深めていただくために毎年開催している企画です。
今年のタイトルは「百の論より一粒の種〜関係性を土壌に〜」です。
オンラインでの情報のやり取りが一層広がる中、ますます「論」に偏りがちに見える社会課題への向き合い方ですが、信頼資本財団では、これまで同様、論よりも、やむにやまれぬ思いで動き出した活動とつながっていく組織でありたいと考えています。
そうした思いを再確認するような節目の2021年「信頼デイ」です。
今のところは、感染拡大防止に努めながら会場ハートピア京都にて開催する予定です。
一方、全プログラムを関係者向けオンライン配信もする予定です。
緊急事態宣言が再発出される場合には、会場開催を取りやめます。
信頼デイ 「百の論より一粒の種〜関係性を土壌に〜」
| 日程 |
|
|---|---|
| 会場 |
ハートピア京都(http://heartpia-kyoto.jp/access/access.html) 3階 大会議室 |
| 会場参加人数 |
【定員に達しましたので、受付を終了しました】 |
| 参加申込 |
|
| 参加資格 |
原則としてこれまで当財団と何らかの取組みがあった方 |
| 参加費 |
無料 |
| タイムテーブル |
※オンラインで同時配信もいたします
<ご挨拶> 13:30~13:50 熊野英介(当財団理事長)
<プログラム1> 13:50~15:20 基調発表と鼎談「百の論より一粒の種」 ゲストスピーカー:石田秀輝さん(東北大学名誉教授)、高木俊介さん(精神科医)
<プログラム2> 15:30~15:50 社会事業塾「A-KIND未来設計実践塾」塾生代表グループからの卒塾発表
<プログラム3> 15:50~16:40 休眠預金等活用助成事業団体からの現場報告
<プログラム4> 16:50~17:10 参加者が関係性を深める時間 ※会場・オンライン両方で行います
<プログラム5> 17:10~17:55 社会事業家セクター構築準備開始宣言
<クロージング> 17:55~18:00 |
■登壇者
合同会社地球村研究室 代表
東北大学 名誉教授
2004年 株式会社INAX(現LIXIL)取締役CTO(最高技術責任者)を経て東北大学教授。2014年より現職。ものつくりとライフスタイルのパラダイムシフトに向けて国内外で多くの発信を続けている。
とくに、2004年からは、自然のすごさを賢く活かすあたらしいものつくり『ネイチャー・テクノロジー』を提唱、2014年から奄美群島沖永良部島へ移住、『心豊かな暮らし方』の上位概念である『間抜けの研究』を開始した。
また、環境戦略・政策を横断的に実践できる社会人の育成や、子供たちの環境教育にも積極的に取り組んでいる。酔庵塾塾長、ネイチャー・テクノロジ研究会代表、サステナブル・ソリューションズ理事長、ものつくり生命文明機構副理事長、アースウォッチ・ジャパン副理事長ほか。
近著: Nature Technology(Springer 2014)、「『超』能力を持つ生き物たち(学研2014)、「それはエコまちがい?」(プレスアート 2013)「自然界はテクノロジーの宝庫」(技術評論社 2013)、「ヤモリの指から不思議なテープ」(アリス館 2011)、「未来の働き方をデザインしよう」(日刊工業新聞 2011)、「自然に学ぶ!ネイチャー・テクノロジー」(Gakken Mooku 2011)、「キミが大人になる頃に」(日刊工業新聞 2010)、「地球が教える奇跡の技術」(祥伝社 2010)、「自然に学ぶ粋なテクノロジー」(Dojin選書 化学同人 2009)ほか多数。
◯高木俊介(TAKAGI Shunsuke)
当財団シニアフェロー
精神科医
京都・一乗寺ブリュワリー 代表
1957年生まれ。
1983年、京都大学医学部卒業。
同年より精神科医として働く。
山の中に隠され社会と隔絶されて鉄格子に囲まれた、日本の社会に染みこんだ差別の象徴としての精神病院で10年、象牙の塔と呼ばれ現実とは隔絶した教育と研究を続けながら専門家という肩書きで社会に君臨する大学病院で10年勤務。
その中で、「精神分裂病」という病名を「統合失調症」に変更する作業にたずさわり、2002年に病名変更が決定されたことを機に大学病院をやめ、充電期間として読書と趣味に2年間ひきこもる。
2004年に、重度の精神障害者の地域生活を多職種による訪問で支援するACT(包括型地域生活支援)をはじめるために、たかぎクリニックを設立。
訪問診療にかけまわっている時に、3・11東北大震災を経験。
学生時代に水俣の支援や反原発運動にかかわりながら、社会人としては何もしてこなかっただけでなく、原発や公害を受け容れてさえいたことを反省し、福島の子どもたちを八丈島で保養してもらう福八子どもキャンププロジェクトをはじめ、9年間続いている。
同時に、地域での精神障害者支援を続ける中で、就労支援の必要性を感じ、
それにむすびつく事業としてクラフトビール醸造のために京都・一乗寺ブリュワリーを立ち上げる。
現在、ACTーK(ACT京都)で訪問診療活動をしながら、一乗寺ブリュワリーを障害者就労支援とむすびつけるべく悪戦苦闘している。