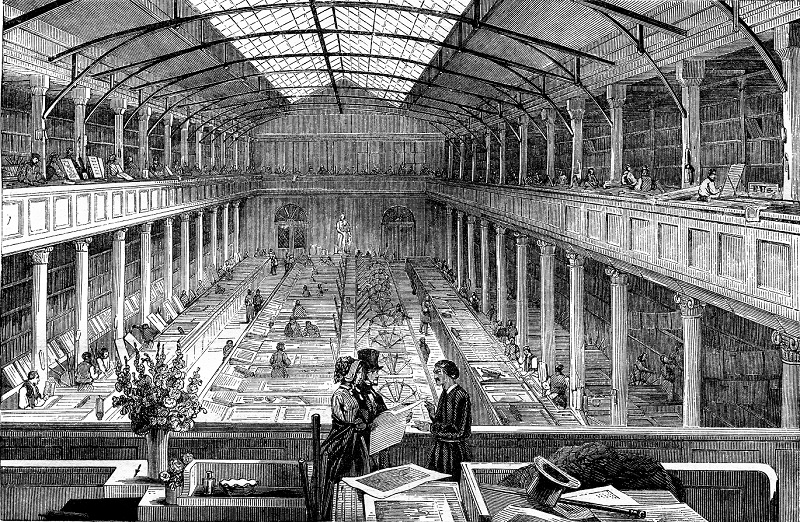「泣くのは嫌だ、笑っちゃおう!」
~希望をもつこと、希望がもてる未来にすること~
~希望をもつこと、希望がもてる未来にすること~
この5月、社会事業家向けの「A-KIND(アカインド)塾」と行政職員向け「未来設計実践塾」という2つの塾を合同した「A-KIND未来設計実践塾」を開講する。
塾としては7期目になる。
その塾を通してもまた伝えていることを書きたいと思う。
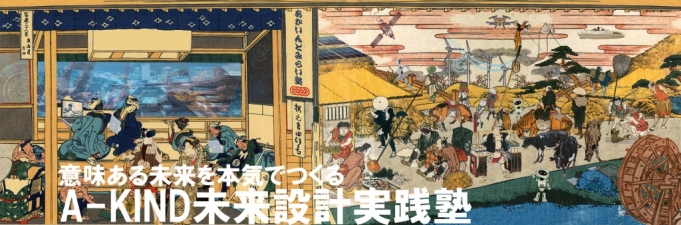
良し悪しは別にして、近現代を通じて構築や変態を続けてきた秩序、その瓦解が進み、次の社会に向けての胎動が既に大きくなっている。
コロナ禍が加速させたことは間違いないが、それ以前からの流れでもある。
世界規模で見れば、気候変動により植生や海洋の状態や農業に変化が大きい時期が続いている。
旱魃が広がり、水不足によって生活できない地域から生まれる環境難民と呼ばれる人々が、国境を越え他国に侵入すれば、紛争が多発するだろう。
このままでは10年後に枯渇するとの予想がある「オガララ帯水層」。
乾燥したアメリカ中部で人々の豊かな生活を支える膨大な量の地下水が枯渇すれば、アメリカ産綿花や小麦やトウモロコシなどに支えられ、結果的には枯渇の一因をつくっている私たち日本人の暮らし、繊維業や畜産、養鶏など衣食にも当然影響が出る。
アメリカだけでなく、中国やオーストラリアやヨーロッパも旱魃に度々襲われている。
こうした環境問題やグローバルサプライチェーンからの調達リスクを鑑みる形で、混乱の中、大量消費を前提とした大量生産社会の経済収縮が進む10年になるのではないか。
日本国内だけを見ると次のようなことが考えられる。
2023年5月頃からコロナ緊急支援融資返済猶予3年の期限を迎えるが、コロナ禍前と後の市場変化で事業計画が立たないところが多く発生する可能性がある。
70歳を超える中小企業の経営者は、およそ245万人と言われているが、そのうち、約127万人が後継者未定の課題を抱えていると中小企業庁調べでわかっており、約22兆円ものGDPが消えてなくなるかもしれない。
1947~49年生まれのいわゆる団塊世代が75歳を超える高齢者となり、国民の3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上という、人類が経験したことのない「超高齢社会」を世界の先陣を切って迎えることから、社会保障費の破綻予報が叫ばれて久しい、「2025年問題」がいよいよ目前に迫っている。
2030年過ぎから、前述した工業化社会の調達リスクがさらに増大し、大量生産大量消費が終焉を迎え、価格競争というビジネスモデルを変換できない企業の継続が困難になる時、失業対策の計画経済の内容を工業モデルにしていては、あらゆる点で持続可能にならないことが見えている。
以上のようなことを踏まえ、コロナ禍により2023年から社会が本格的混乱期に入ると仮定するなら、この2年が備える時期ということになる。
その時にまず必要なのは、「希望」である。
「希望」といった、人が幸福を感じる心に経済の解を求めるなど科学的ではないという経済論が長く社会を支配してきた。
しかし、この点を無視して語る経済論が、格差や差別、大量殺戮や孤立を生んできたことは近現代の歴史を見れば明白だ。
人類は、想像力を発達させ、仲間と共に生存域を広げる中、「孤立したくない」という共通した感情をもつ生物となった。
「独りでいたい、孤独を楽しむ」という、「選択できる独り」について語っているのではない。
否応なく関係性を断ち切られ、社会で地域で職場で学校で家庭でその他のコミュニティで孤立させられてしまうこと、それを恐れる感情についての話である。
したがって、良質な社会関係性をもつことができるなら、希望は生まれ、さらに、それを広げる社会にしていこうという気持ちが生まれ、関係性の豊かな社会になっていくだろう。

孤立は、社会環境による構造的な部分と自らの精神による部分の両方によってつくりだされていく。
「心こそ 心迷はす心なれ 心に心 心ゆるすな」と鎌倉時代に得宗家専制政治の基礎をつくった北条時頼が述べている。
損得勘定をする「心」と豊かな関係性を欲する「心」の葛藤、権謀術数の社会を生き抜いた人物ゆえに成した言葉だと、私は捉えている。
現代において、損得勘定に重きをおく生き方をすれば、工業社会において、自らの能力を損得の経済的判断基準にされることを無条件で受け入れてしまうことになる。
たとえば、芸術や哲学のようなことを学びたいと思っても、「そんなことを学んでも生きていけない」と否定され、農業や林業や漁業のように、思いどおりにならない自然を相手にする仕事をしたいと言っても、「もっと楽して儲かる事があるはずだ」と否定され、近代システムから価値をはかりにくい職場もまた否定されてしまう。
効率的に得になる方法を学べば、人生は楽になると教育されて大人になる社会が続いてきた。
しかし、その生き方には「安定して成長する」という機械的な条件がついていることは教えられない。
人の心、人生は不安定なものである。
病気や怪我をしたり災害にあう可能性があるし、出産をすること、育児や介護に関わることがある。
齢を重ねると物忘れをし、目が悪くなり、耳も遠くなり、いずれ一人で移動ができなくなる。
そのような自然の一部として生きる人間の特徴は、効率的に得をする方法からは排除されているが、必ず個々に生じるものである。
つまり、不確実で不安定で不連続な「自然の営み」よりも、確実で安定的で連続性のある「人工的で機械化された営み」が評価され、その機械化された社会の一員になる訓練を課して、経済的豊かさによって人生における自由の獲得と不安の解消ができるという空想の中で社会は動いてきた。
しかし、そのように人間の尊厳を経済に依存し過ぎた近代システムの社会が、この先2年を過ぎる頃からさらに混乱し、劣化していくとしたら。
人の心は、経済力ではかれるものではなく、それに付随した能力や学歴や家柄や社格ではかれるものではもちろんない。
豊かな関係性をつくろうという人間性をまずもち、周囲を思い、力を尽くしていくことで、不安が小さくなり、心が自由になり、「希望」が見えてくることは多い。
希望をもちにくい人の手助けが少しずつできるかもしれない。
そして、その希望が関係性の豊かな社会を広げる種になっていくと考えている。
希望は、見ようとする者、つくろうとする者にしか感じられない。
コロナ禍で理不尽な経験や不合理な状況を経験した我々は「豊かな関係性」で社会を立て直す準備に入る方向に舵をとりたい。
豊かな関係性をつくるということは、効率より手間を選ぶことであり、自分だけを優先するのではなく、家族や仲間を含む社会を同時に考えることである。
「部分の総和は、全体を超える」と考えること。
自然から、「何一つ、一方的に強いものは無い」と学ぶこと。

孤立したくないという不安を増幅させ、効率的に楽になることを考え、変革期を迎えているこれまでのシステムにしがみつくのではなく、希望に火を点け、希望を探しだす心に寄り添い、社会関係性資本を育み、関係性豊かな未来への準備に入ろう。
2021年5月10日
信頼資本財団 理事長 熊野英介